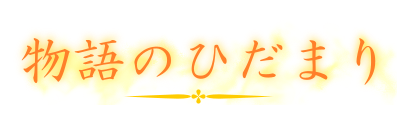私的体験
実家のある海沿いの集落から平坦地を1キロほど陸側に入ったところに、その坂道はあります。小高い丘の取りつきの斜面に沿って刻まれた道は曲がりくねり、四つの折り返しを経て、ようやく丘の頂上へとたどり着きます。
江戸時代の中期、丘の山林は三重の味噌問屋によって大豆畑として開拓されました。
江戸に味噌を供給するには三重から運んでいては追いつきません。江戸で味噌を生産しようとすれば原料となる大豆も近傍からの調達が必須です。
集落には内陸で採れた米や竈の燃木を船で江戸に送る集積所がありました。この地で大豆を栽培すれば、かんたんに江戸に運べる。そんな思惑から僕の故郷に白羽の矢が立ったのでしょう。
資料は残されていませんが、おそらくその道も商人の資金によって開かれたものと思われます。おかげで頂上の奥に村人は広い畑地を開墾することができました。
さてその坂道を上りきった終点に小さな馬頭観音が祀られています。大豆畑の開墾に、そして収穫物の荷出しに馬が酷使されたに違いありません。その労をねぎらうための塚なのでしょう。
子どもの頃、正月になるとしめ飾りをその馬頭観音に供えてこい、と祖父に命じられ、怖くて嫌がった思い出があります。その名から馬の首が埋められていると本気で信じていたからでした。
別の場所に新しく街道が作られ、丘の上に続く坂道はいまはほとんど使われなくなりました。しかしそれが命を持っていた日々はたしかにあり、ひとの息吹がありました。それを思うと胸のどこかで人の営みへの愛おしさが沸き上がります。
僕は似たような感慨を最近二つの物語から得ました。
ジョン万次郎と長平の時空を超えた出会い
井伏鱒二に「ジョン万次郎漂流記」という作品があります。説明するまでもないでしょうが、ジョン万次郎(ジョン・マン)は実在した人物で、漁師の一人として乗り込んだ船で遭難し、アメリカの捕鯨船によって救出されたのち、日本の開国に貢献しています。当然詳細な資料が残されており、井伏鱒二も史実をもとに物語を紡いだものと思われます。そこにつぎの描写があります。
頂上はかなり広い平地になってゐて、そこには石でたたんだ一つの井戸と、墓石と思はれる長めの石が二つあった。井戸には少量の濁り水が溜り、墓石は痛く風化してゐた。
出典:「ジョン万次郎漂流記」井伏鱒二自選全集第2巻 新潮社
1841(天保12)年1月、ジョン万次郎は八丈島の先「鳥島」に漂着し、同年5月まで生活しています。引用はジョン万次郎が島で目にした光景です。
さて、遡ること四十数年前、その場所には土佐の船乗り(舵取り)長平が立っていました。
こちらも資料を精査し物語に仕立てることにおいて力を発揮した吉村昭が「漂流」という作品を残しています。
物語の主人公長平は米俵を運ぶ仕事の帰り、空船で暴風に会い遭難します。そして命からがらたどり着いたのが「鳥島」でした。およそ12年間、後に同じように漂流した船乗りたちと無人島生活を送る中、飲料水を確保するため、彼らのとった行動が克明に(もちろん素晴らしい想像力によって)記された部分があります。
池を掘る作業は、五月末に終了した。広さは十坪(三十三平方メートル)深さは一間(一・八メートル)ほどであった。(中略)雨はやみかけていて、あたりは霧雨に煙っている。池のふちには、多くの者たちが立ったりしゃがんだりしていた。鳥の羽の蓑を着ている者もいたが、大半は半裸だった。長平は、彼らの傍に立った。かれらは、口々に、「三寸(九センチ)ぐらいだ」「いや四寸五分(一三・五センチ)はある」などと明るい声をあげている。それらは、池の底にたまった水の深さであった。長平の眼に、熱いものがにじみ出た。
出典:「漂流」吉村昭 新潮文庫
島は火山島であったため土壌は礫質で穴を掘っただけでは水を貯めることはできません。そこで重次郎という人物が漆喰で固めることを提案し、彼らは海草や葦などを土に混ぜた漆喰で池の漏水を防ぎました。
1797(寛政9)年6月、長平たちは鳥島を脱出します。万次郎は44年後まさにその池を「石でたたんだ一つの井戸」として目にしたのです。
長平たちの歓喜をそのとき万次郎は知る由もありません。後世に生きる僕は二人の出会いに立ち会い、一人胸を熱くしているのでした。
記事一覧掲載の画像:photo by GEORGE DESIPRIS / Pexels