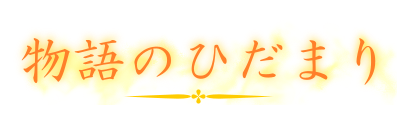このブログ記事は村上春樹著「騎士団長殺し」を考察したものです。第1部、第2部すべて読んだ方を対象としています。読む前に内容を知りたくない方はここで閲覧を中止されることを強くお勧めします。
またこの考察は一個人の見解であり、他者のそれを否定するものではありません。できればコメントをいただけるとうれしいです。本書の世界をいっしょにたのしみながら、さらに理解を深めていければと思います。
なおここではイデアを真実、メタファーを表象としてとらえています。国語の授業的な暗喩表現にしばられず、すべての表象的なるものをメタファーと呼ぶことにします。
雨田具彦が最後に見たものは何か
多くの方がナチスの服を着た男を刺し殺し、思いを遂げたと解釈されたのではないでしょうか。しかしそれでは恋人のメタファーとして描かれたドンナ・アンナが「大きな悲鳴をあげようとしているように」口を開け、驚愕の表情を浮かべていることの説明がつきません。
雨田具彦は刺し殺される騎士団長に自分自身の姿を見たのではないでしょうか。つまり若き雨田具彦(「放蕩者ドン・ファン」)が老いた雨田具彦(騎士団長=ドンナ・アンナを愛する者)を刺すというシーンです。
初版第2部314ページには、こう書かれています。
雨田具彦は自分が実際には成し遂げることができなかったことを、偽装的に実現させた。起こるべきであった出来事として(*1)
彼は政府によって救出されおめおめと一人生還します。そこには恋人を裏切ったという「恥」があります。だから地位の約束された「洋画」を続けるわけにはいかなかった。
彼はその時点で自死を願ったのかもしれません。しかし自死するにもすでに弟に先を越されてしまった。「家」の「恥」を重ねるわけにはいかなかったのでしょう。そこで彼は絵の中での自殺を思い立ちます。その思いをイデアによって真実のものとし成就させたというわけです。
なぜ秋川まりえは無事だったのか
免色邸に忍び込んだ秋川まりえは拍子抜けするほど何事もなく邸から脱出します。しかしそれには理由があります。
まず主人公は彼女の「居場所を知り」「取り戻す」ことを願っていた。では「取り戻せない」状況とは何か。それは時間に縛られない世界と並行宇宙を視野に入れる必要があります。
たとえば金曜日の午後の段階で
(1)ドーベルマンに彼女が襲われる可能性
(2)テラスでスズメバチに刺される可能性
(3)亡き母の衣装(メタファー)の力もむなしく免色の「二重メタファー」に見つかる可能性
(4)ゲストルームに水と食料がない可能性
そして火曜日の朝に
(5) クリーニングサービスが何らかの事情で来なくなる可能性
これらは結果的に回避され、彼女が「もとの彼女のまま(何も損なわれることなく)」無事に免色邸から抜け出す、という世界(宇宙の一つ)が実現されます。つまり「秋川まりえを取り戻す」ことができた。
そのためには、主人公が「試練」を受けなくてはなりませんでした。「試練」をくぐりぬけることに失敗していたら、因果は遡行し、とんでも世界へと墜ちてしまったかもしれません。
祠の裏の穴は何だったのか
イデアが召喚される場所ではないでしょうか。
人々は偶然にも時空の裂け目を発見し「真実」に出会える場所として利用していた。しかしやがて人々はイデアを野に放ち、イデアを求める人のところに行かせてはならないと考えはじめます。「人は見るべきものを見ることが幸福」とは限らないという知恵を過去に起きた何らかの事件を通し学んだからです。だから畏れ多きものとして崇め厳重に封印した。
初版第1部451ページで騎士団長はあきらめにも似た口調でつぎのように述懐しています。
真実とはすなわち表象のことであり、表象とはすなち真実のことだ。そこにある表象をそのままぐいと呑み込んでしまうのがいちばんなのだ(*1)
主人公は「自分自身に出会うことができる場所」で「真実の自分」を発見することで、祠の裏の穴にイデアとして出現したものと思われます。
免色は「顔のない男」のメタファーである
初版第1部106ページ第6章のタイトルは「今のところは顔のない依頼人です」となっています。そして物語に色=個性=顔を免れた免色が登場します。
免色は土木作業の手配というかたちで鈴の音で存在を知らせた騎士団長と主人公の出会いの“橋渡し”をします。それはまた騎士団長と「騎士団長殺し」の絵が一対の必然として揃う“橋渡し”でもありました。
一方「顔のない男」は洞穴=風穴の川で“橋渡し”の役目を担っている。
これらのことから洞穴がイデアの世界であるとすれば免色は「顔のない男」のメタファーであると考えられます。
主人公は免色の顔をこれまでにない手法で描き上げます。するとそのイデアである「顔のない男」が自分の顔を描けと追ってくる。「プロローグ」に置かれたシーンはこの物語の深化を予言して不気味です。
なお村上春樹はかつてインタビューでこう答えています。それは父が中国に出征し体験したと思われることについて述べた後でした。
僕は事実を知りたくない。想像力の中に閉じ込められた記憶がどんな結果を生み出すのか、それだけにしか興味がない(*5)
これは初版第1部420ページでの免色の言葉と符合します。
私は揺らぎのない真実よりはむしろ、揺らぎの余地のある可能性を選択する(*1)
当然のことながら、免色は作者自身の分身でもあるわけです。
「あらない」は般若心経である
騎士団長の口調は独特で、その登場によって物語の空気は一変しました。デヴィッド・リンチの映像作品に登場する小人のような異様さはなく、むしろ滑稽さがトリックスターとしての足取りを軽快にし有効です。とりわけ彼の特徴的な言い回しである「あらないよ」に心を持っていかれた読者は多いはず。
「あらない」とはどのような意図で使われているのでしょう。
騎士団長は「あらない」を否定の際に用います。ならば普通は「ない」です。ではなぜ「あら」がついているのか。それは「あらない」が「ある」の未然形だからです。そう中学生のとき必死に覚えた動詞の五段活用、未然・連用・終始・連体・仮定・命令です。あらない・あろう・あります・ある・あるとき・あれば・あれ。通常の日本語では「あらない」だけが変形し「ない」となります。しかしキャラクターに個性を与えるフックとしてあえて使った。
ただ作者はそれだけで「あらない」を用いているわけではないと考えます。
「あらない」を“ある=在る”と“ない=無い”に切り分け、その対比を際立たせるためではないかというのが僕の見立てです。
つまり“存在していることは存在していないこととつねに表裏一体である”、それほど世界は危ういものであると言っているように思うのです。
それはまさに般若心経が唱える「色は空、空は色」であり、ボーアの量子論が証明する消滅し、軌道を変えて出現する電子の振る舞いにほかなりません。さらに言えば本ブログで紹介した“即非の理論”に通じるものでもあります。
前述のとおり免色はこう語っています。
私は揺らぎのない真実よりはむしろ、揺らぎの余地のある可能性を選択する(*1)
物語のなかで彼はアンチ的な役割ですが、これもまた真理でしょう。「真実」がイデアであるとすれば「揺らぎの余地のある可能性」はメタファーです。つまり彼はメタファーに生きると宣言しています。
またこれはイデアを追及する“観念”よりも、揺らぐ“現実”を選択することをも意味します。
同第1部388ページで免色はこうも言っています。
(人類は)大脳皮質がなければ 抽象的思考をすること 形而上的な領域に足を踏み入れることはなかった(*1)
「あらない」を繰り返す“現実”を選択した彼は“人間性を捨て去る覚悟”で秋川まりえを望んでいたわけです。彼の凄みはこんなところにも隠されています。
ラブホテルの女と「二重メタファー」
初版第2部の376ページで主人公による「二重メタファーとは何か?」という問いに
ドンナ・アンナが答えます。
それはあなたの内側にある深い暗闇に、昔からずっと住まっているもの(*1)
そして主人公は
白いスバル・フォレスターの男だ、と私は直感的に悟った(*1)
では「白いスバル・フォレスターの男」が表象するものは何でしょうか。僕は「暴力」ではないかと考えます。
そして男が「二重メタファー」であるとすれば最初のメタファーは何か。それはラブホテルで首を絞めることになった女をさしています。つまり主人公の「欲望」の表象として現れた女が「暴力」に転化した。「二重メタファー」はこのように本来あったものからまったく異なったものへと形をかえる“隠喩の隠喩”であるところに怖さがあります。
登場人物を三角計測してみる
主人公を観測の中心点として主要な登場人物(モノ)を2点に置いてみると興味深い関係性が浮かび上がります。とくに秋川まりえと秋川笙子。雨田具彦と雨田政彦。それぞれがイデア(真実)的なものとメタファー(表象)的なものを演じているのがわかります。
遠くから眺めると良家のお嬢さま、雨田家の人間という共通の姿をしているのに、近くでつぶさに観察するとそれぞれの姿は大きく異なります。そして物語の中で秋川笙子と雨田政彦は主人公にとってどこか相容れない存在として置かれている。
主人公がイデアと向き合う物語にあってそれは必然的な配役といえます。
また秋川まりえと免色渉を2点に置いてみると、イデア(真実)的なものとメタファー(表象)的なものの対決が生まれます。彼女を免色邸に忍び込ませたことで免色の邪悪な正体を「諸君」は見ることになります。
予定調和を宣言したサスペンス
「騎士団長殺し」は村上春樹の長編としてはめずらしく物語が収束して終わります。しかもそれはきわめて早い段階から宣言されている。妻と別れ、よりを戻すまでの数ヵ月間に起きた出来事と明かしていることから、どんな事件が起きても必ず解決され平和裏に収まることが約束されています。
しかし奇妙なことにその宇宙には破れがあって新たなビッグバンがすでに始まっている。それが「プロローグ」の「顔のない男とペンギンのお守り」のエピソードです。予定調和をあらかじめ否定し、ゆがみを与えたことで、この物語全体のサスペンスとしてのリアリティが担保されているように思います。
村上春樹の作品を「出来事が中途半端に残されたまま終わってしまうのが気持ち悪い」と毛嫌いする方がいます。しかし僕はそれこそが人生ではないかと思います。人生とは結論が用意されているものではない。何事も途上であり、結果らしきものも始まりにすぎなかったりする。当事者が出来事の意味を理解する間もなく過ぎ去っていくのがメタファー。騎士団長が言うように、そして秋川笙子がそうであるように、メタファーをそのまま呑み込みやり過ごしているのが僕らの日常です。
村上春樹が敬愛するレイモンド・カーヴァーの短編のように、それが小説のリアリティではないかと考えます。そして読者が普段できない出来事の解釈を、それぞれが自分の人生観から導き出すことが小説を読む醍醐味ではないでしょうか。
本作では読者に収束を提供しながら、なおかつ破れも保持している。綾のかけ方に唸ります。
「羊をめぐる冒険」の終着点か
「羊をめぐる冒険」初版210ページで主人公はこう語ります。
僕は毛布にくるまって、ぼんやりと闇の奥を眺めた。深い井戸の底にうずくまっているような気がした(*2)
ここから「鼠」と主人公の対話が始まります。
「深い井戸の底」は「異界と対話し浮遊している自分を固定化するための思考の場」であり、たぶんこれがそうした役割としての「井戸」の最初の登場ではないでしょうか。(*3)
その後「ねじまき鳥クロニクル」では世田谷の住宅街のなかにある実際の井戸として主要なモチーフとなります。また「ノルウェイの森」でも井戸は登場する。
本作で主人公は井戸を下りるのではなく、井戸の底のさらにその底をめぐった後、自らを発見し、井戸の中で“生まれ直し”ます。その過程で語られるのは思考の場としての井戸の底の構造とその作用。なぜ村上春樹の作品に「井戸」は登場しなくてはならないのか、ここにすべてが語りつくされたように思えます。
かつて「羊をめぐる冒険」は「風の歌を聴け」「1973年のピンボール」に続く長篇第三弾として「ラスト・アドベンチャー」のキャッチフレーズで発売されました。しかしご存じのとおり旅は終わることなく、つぎつぎと新たな地平が拓かれてきました。
僕は彼の次作がたのしみでなりません。
Reference
参照:*1 「騎士団長殺し」村上春樹著 新潮社 *2 「羊をめぐる冒険」村上春樹著 講談社 3 「村上春樹『井戸』再考」武井昭也著 Hosei University Repository ではデビュー作「風の歌を聴け」ですでに「井戸」が登場していると指摘されています。本ブログでは異界とつながる「井戸」としての出発点が「羊をめぐる冒険」にあるのではないかという見解です。