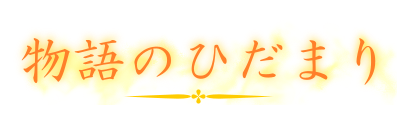数年前、事務所を解散し鬱々とした日々を送っていたころ、その本に出会った。
あれはブックオフだ。揺るぎないものにすがりたくて、岩波の古典の棚の前に立ち偶然目にしたのがキェルケゴールの「死に至る病」だった。フランクルの「夜と霧」(みすず書房)といっしょに買い求めたのだから相当にまいっていたのは確かだ。
「死に至る病」というタイトルに惹かれて手にしたが、一方でそのストレートな言葉が怖かった。こころに抱える暗黒に引きずり込まれそうで、そこから抜け出せなくなるのではないかと感じた。だから思い切って手に入れたにも関わらず、最初は机の横に放置していた。数ヵ月後やっと手にしたが、読み終えるのにさらに1年を要した。
キェルケゴールが「死に至る病」と定義したのは「絶望」だった。
物理的に外形が視認できるものは記述しやすいが、観念の詳細をとらえ伝達することは容易ではない。彼は「絶望」の全貌をつまびらかにしようとした。そのため記述は細部にわたり、読者は部位の位置を正しく認識するのに思考しなければならない。難解ではあったが、その正確な描写によって、僕は自分の鬱たるこころの適切な場所にメスを入れ、解剖観察することができた。
「絶望」を客観的に捉えるこの本は、じつは「希望」の書でもあった。
*
彼が「絶望」から脱するための“蜘蛛の糸”として定義したのはキリスト教における「神」だった。
象徴的な一節があるので引用したい。
牝牛に対して自己であるような牧人は非常に低い自己である。奴隷に対して自己であるような主人もまた同様である。本来この両者はいかなる自己でもない。――尺度が存在しないからである。これまで単に両親を尺度にしていた子供が、成人にして国家を尺度にするに至るとき自己となる、――だがもし自己が神を尺度にするに至るならば、何という無限のアクセントが自己の上に置かれることであろうか! 自己が何に対して自己であるかというその相手方が、いつも自己を量る尺度である。
出典:岩波文庫「死に至る病」キェルケゴール著 斎藤信治訳
自己(あるべき自分)を何に求めるか。牡牛や奴隷(歴史的用例としてご容赦を)といった下等なものに求めていては自己と呼べるものは獲得できない。ひとは両親から自己を学び、国家(社会)に自己を求めるに至り大人となる。そしてさらなる高みを求めようとするならば神を自己とせよ、というわけだ。
*
神を自己としない異教徒の「絶望」こそ「死に至る病」であるとこの本は断じている。僕はキリスト教徒ではないので異教徒の部類なのかもしれないが、それでも救いを求めることはできる。
神を「最上の良心」に置き換えるとわかりやすいかもしれない。
僕はいま何を尺度とした「あるべき自分」に「絶望」しているのか。その対象を見極めることで新たな「希望」がわいてくることに気づかされる。すなわち「最上の良心」を獲得するチャンスは無限にある、とこの本は教えてくれているのだ。
*
学校に、先生に、両親に「絶望」し、命を絶ってしまう子どもがいる。気づいてほしいのは、きみの自己はまだ生まれたばかりであり、とても脆く小さいものだということだ。あえて言えばそれらはまだ「絶望」するに値しない。もっともっと「絶望」しがいのある自己へと鍛えるべきだということだ。高い次元の「絶望」は、すぐさまつぎの「希望」となって立ち上がる。「最上の良心」は無限に存在し、鍛え上げられた自己が自ずとそれを求めるようになるからだ。それこそが人生を謳歌するということではないか。
きみにこの本をすぐに読んでほしいとは思わない。「絶望」を重ね「絶望」に愛着がわき始めてからでも決して遅くないと思うからだ。いつかその気になって読んだとき、きみは「絶望」をしっかりと抱きしめるだろう。それまできみは生きなければならない。残酷なようだが、生きなければならない。
記事一覧掲載の画像:photo by Valeria Boltneva / Pexels