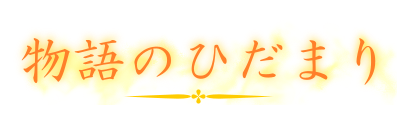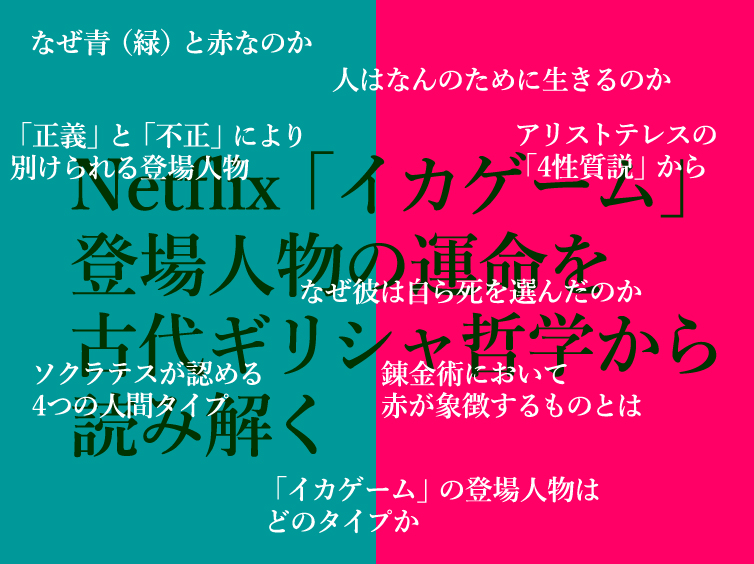東京渋谷の地下鉄ホーム。「田園都市線」の下りの先に彼女の住む家があった。僕の事務所は表参道にありホーム反対側の上りだった。
もう別れて数年経ったある日、そのホームで思いがけず彼女の香水が鼻をかすめた。熱情と畏れの入り混じったあいまいな気持ちが湧いたが、体は即座に反応し辺りを見回した。
もし彼女を見つけたら、僕はなんと声を掛けただろう。とても会いたかったが、会えなくてよかったのかもしれない。
先週末、永井荷風の「濹東綺譚」を読んだ。
彼はそこで劇的なシーンの描写をベタと評した。
たとえば主人公と情を交わすお雪の登場は突然の雷雨の傘の下である。
いきなり後方から、「旦那、そこまで入れてってよ。」といいさま、傘の下に真ッ白な首を突ッ込んだ女がある。
出典:永井荷風「濹東綺譚」岩波文庫
映画のシーンであれば、観客をぐぐっと引き込むきわめて印象的なものであるはずだ。しかしこの描写を荷風は数ページ後に弁明する。
夕立が手引きをしたこの夜の出来事が、全く伝統的に、おあつらい通りであったのを、わたくしはかえっておもしろく思い、実はそれが書いてみたいために、この一遍に筆を執り初めたわけである。
出典:永井荷風「濹東綺譚」岩波文庫
そしてさらに巻末において劇的なエンディングの可能性に言及する。
もしここに古風な小説的結末をつけようと欲するならば、半年あるいは一年の後、わたくしが偶然思いがけないところで、すでに素人になっているお雪にめぐりあう一節を書き添えればよいであろう。
出典:永井荷風「濹東綺譚」岩波文庫
僕があのとき望んだのはまさに「古風な小説的結末」だった。
なんとも野暮な男の妄想であったことに齢60を過ぎようやく気付かされたというわけである。
ひとはついドラマチックを求めがちだ。しかし日常の隅々に佇む小さな感慨こそ我が生を満たす主題であることにもっと注意を払うべきだろう。
その意味で荷風は達人だったのかもしれない。